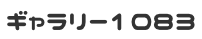-

BOKUSAIくん AI墨彩画家 「イギリスの名所を歩く女性」
¥50,000
AI墨彩画家のBOKUSAIくんの作品集です。 今回のテーマは「イギリスの名所を歩く女性」 バッキンガム宮殿 ビッグベン 湖水地方 ストーンヘンジ ヘンリー通り カンタベリー コッツウォルズ 順不同 侘び寂びのあるシンプルな魅力で墨彩画を描いていきます。 どうぞご覧ください。 ※金額は仮のものです。お問い合わせから、ご相談で決定します。
-

BOKUSAIくん AI墨彩画家 「アメリカの名所を歩く猫と女性」
¥50,000
AI墨彩画家のBOKUSAIくんの作品集です。 今回のテーマは「アメリカの名所を歩く猫と女性」 ゴールデンゲートブリッジ フィッシャーマンズワーフ ラスベガス ヨセミテ国立公園 グランドキャニオン オールド・フェイスフル・ガイザー 順不同 侘び寂びのあるシンプルな魅力で墨彩画を描いていきます。 どうぞご覧ください。 ※金額は仮のものです。お問い合わせから、ご相談で決定します。
-

BOKUSAIくん AI墨彩画家 「ニューヨークの名所を歩く女性」
¥50,000
AI墨彩画家のBOKUSAIくんの作品集です。 今回のテーマは「ニューヨークの名所を歩く女性」 タイムズスクエア 自由の女神 セントラルパーク 5番街 ブルックリンビレッジ ブロードウエイ モーガン図書館 順不同 侘び寂びのあるシンプルな魅力で墨彩画を描いていきます。 どうぞご覧ください。 ※金額は仮のものです。お問い合わせから、ご相談で決定します。
-

BOKUSAIくん AI墨彩画家 「パリの名所を歩く女性」
¥50,000
AI墨彩画家のBOKUSAIくんの作品集です。 今回のテーマは「パリの名所を歩く女性」 エッフェル塔 凱旋門 シャンゼリゼ通り ノートルダム大聖堂 パンテオン コンコルド広場 セーヌ河 順不同 侘び寂びのあるシンプルな魅力で墨彩画を描いていきます。 どうぞご覧ください。 ※金額は仮のものです。お問い合わせから、ご相談で決定します。
-

BOKUSAIくん AI墨彩画家 「始まりの灯」
¥50,000
こちらは墨彩画専門のAI画家として育成してきた「BOKUSAIくん」の作品集です。 微妙なタッチや色合いをうまく表現するように学習させています。 BOKUSAIくんの詳しくはこちら。 https://www.toukiya.net/blog/2024/02/24/203511 ご希望のものがありましたら、お問い合わせより連絡ください。 ●このページの金額は仮のものです。 ご注文の際はお問い合わせからご連絡の上、金額を決定してからご購入ください。
-

デジタルアートの作品集 vol4 動物集まれ AI画像生成
¥2,000
デジタルアートの作品集 vol4です。AI画像生成 注文制作用サンプルのデジタルアートを追加していきます。 ●こちらは動物の仮装系で仕上げています。 ご希望のものがありましたら、お問い合わせより連絡ください。 ●このページの金額は仮のものです。 ご注文の際はお問い合わせからご連絡の上、金額を決定してからご購入ください。
-

デジタルアートの作品集 vol5 ロボット登場 AI画像生成
¥2,000
デジタルアートの作品集 vol5です。AI画像生成 注文制作用サンプルのデジタルアートを追加していきます。 ●こちらはロボット系で仕上げています。 ご希望のものがありましたら、お問い合わせより連絡ください。 ●このページの金額は仮のものです。 ご注文の際はお問い合わせからご連絡の上、金額を決定してからご購入ください。
-

デジタルアート作品集 vol3. イラスト仕上げ AI画像生成
¥2,000
デジタルアートの作品集 vol3 です。AI画像生成 注文制作用サンプルのデジタルアートを追加していきます。 ●こちらはイラスト風に仕上げています。 ご希望のものがありましたら、お問い合わせより連絡ください。 ●このページの金額は仮のものです。 ご注文の際はお問い合わせからご連絡の上、金額を決定してからご購入ください。
-

デジタルアート作品集 vol2 リアル画像集 AI画像生成
¥2,000
デジタルアートの作品集 vol2 です。AI画像生成 注文制作用サンプルのデジタルアートを追加していきます。 リアリティにこだわったリアル画像になります。 ご希望のものがありましたら、お問い合わせより連絡ください。 ●このページの金額は仮のものです。 ご注文の際はお問い合わせからご連絡の上、金額を決定してからご購入ください。 詳しくはこちらのページも参照してください。 https://www.toukiya.net/items/72821722
-

ロゴ・マスコットキャラクターのサンプルです AI画像生成
¥6,000
注文制作用サンプルのデジタルアートを追加していきます。AI画像生成 こちらはロゴとマスコットキャラクターのサンプルです。 ご希望のものがありましたら、お問い合わせより連絡ください。 ●このページの金額は仮のものです。 ご注文の際はお問い合わせからご連絡の上、金額を決定してからご購入ください。 詳しくはこちらのページも参照してください。 https://www.toukiya.net/items/72821722 このページの更新 2023/03/28 カフェのロゴ・マスコット他追加
-

デジタルアート 作品集vol1 動物キャラクター AI画像生成
¥2,000
注文制作用サンプルのデジタルアートを追加していきます。AI画像生成 ●こちらは動物キャラクターものです。 ご希望のイラストがありましたら、お問い合わせより連絡ください。 ●背景も透過にできますので、LINEスタンプなどにも利用できます。 ●このページの金額は仮のものです。 ご注文の際はお問い合わせからご連絡の上、金額を決定してからご購入ください。 詳しくはこちらのページも参照してください。 https://www.toukiya.net/items/72821722 このページの更新 2023/03/28 ゴリラのラガーマン他追加 2023/03/25 トイプードルゴルフ他追加 2023/03/24 子猫野球他を追加。
-

注文品を承ります デジタルアート AI画像生成
¥18,000
デジタルアートの注文品を承ります。 画像生成AIを使って、ご希望のデジタルアートを制作します。 サンプル画像のように、いろんな種類のAIアートを制作可能です。 ●注文品に限っては類似性のチェックをして、著作権を尊重しての販売をいたします。 ●大きさは6000ピクセル位まで可能です。 紙のサイズ換算で50✖️70センチくらいまで。 ●ご希望のアートを制作しますので、お問い合わせからご相談ください。 (ご相談は無料ですが、2回目位からのやり取りは住所、氏名をお願いします) ●アート系の制作物は本人のイメージと合わない場合もあるため、あまり凝った内容のご注文はお受けできない場合があります。ご了承ください。 初回のご質問は遠慮なく「お問い合わせ」からご連絡ください。 ●こちらのページの金額・購入後のダウンロード画像は仮のものです。必ずお問い合わせからご連絡の上、金額を決定してからお買い上げください。 ●AIアートの需要としては店舗のロゴ、ホームページへの画像やドット絵にしてSNSなどのアイコン、紙のチラシやポスターの素材などをおすすめします。 ●これからの時代はイラストや絵をAIで描く時代になっていきます。 そのためのサンプル素材としてもご利用ください。 ●納品は画像1枚の価格です。 ご注文されるとサンプル画像を制作します。4枚で1セットになっています。その中からご希望のものを1枚選んで頂き、大きさを指定サイズに変えて納品します。 ●NFTアートには今のところ適応していません。 今後、適応する場合もあるかと思いますが、規約の範囲内ですと、若干NFTには不向きのような感じです。 ですので、当方ではNFT化せずに販売しています。 (NFTとは、所有者情報を付けての販売の事) すでにAIアートの画力は人力を超えています。 大きさも数年以内には巨大壁画などにも対応していくでしょう。 これからのAIアートをぜひ楽しんでください。
-

注文品をお作りします 陶磁器
¥50,000
陶磁器の注文品を承ります。 あなただけの一品をお作りします。 ご注文の品がありましたらお知らせください。 ●価格例 ・湯呑みを一点 約30000円から ・ぐい呑みを一点 約50000円から ・抹茶茶碗を一点 約150000円から ・いわゆる年代物の写し 約300000円から応相談 (写しを銘記します。gansaku系は一切作りませんのでご了承ください) ・テレビ 映画などで使う小物類 価格応相談 (テレビドラマ、CMなどの制作実績あり) 作家名 行雲(こううん) 桐箱付き ● ご依頼の際はお問い合わせからご相談ください。 ※こちらのページの品代は仮金額です。 お問い合わせから金額を決定→その後購入してください。
-

陶芸・陶磁器 ハウスHati
¥32,000
陶芸・陶磁器のハウス型の植木鉢です。横のポットに植物を入れます。 作家名 行雲(こううん) 制作工程はyoutube にて公開しています。 ぜひご覧ください。
-

陶芸・陶磁器 麻ヒモHati
¥22,000
陶芸・陶磁器の麻ヒモで区切る植木鉢です。釉薬はオリジナルの鉄紫釉。なかなか渋いです。 作家名 行雲(こううん) 制作工程はYouTubeで公開しています。 ぜひご覧ください。
-

陶芸・陶磁器 黒釉麻ヒモ鉢002
¥21,000
黒釉で焼かれた陶芸・陶磁器の麻ヒモのデザインの植木鉢です。 ヒモを境に二手に分かれて植えられます。 作家名 行雲 (こううん) 制作工程はyoutube にて公開しています。 ぜひご覧ください。
-

陶芸・陶磁器 黒釉斜め鉢001
¥12,000
黒釉で焼かれた陶芸・陶磁器の植木鉢です。 丸型から斜めに切り込みを入れて、おしゃれに仕上げてます。 作家名 行雲(こううん) 制作工程はyoutube にて公開しています。 ぜひご覧ください。
-

陶芸・陶磁器 白化粧鉄絵浅鉢
¥18,000
白化粧で焼き上げた陶芸・陶磁器の植木鉢です。 鉄絵で文様をうってあります。 作家名 行雲(こううん) 制作工程はyoutube にて公開しています。 陶芸教室 陶八さんチャンネル https://m.youtube.com/channel/UC62ECLVxfkoq03yfWJqFlXA ぜひご覧ください。
-

陶芸・陶磁器 白化粧植木鉢
¥15,000
白化粧で焼き上げた陶芸・陶磁器の植木鉢です。 素直な形で仕上げました。 作家名 行雲(こううん) 制作工程はyoutube にて公開しています。 陶芸教室 陶八さんチャンネル https://m.youtube.com/channel/UC62ECLVxfkoq03yfWJqFlXA ぜひご覧ください。
-

陶芸・陶磁器 白化粧靴型鉢
¥11,000
白化粧で焼き上げた陶芸・陶磁器の植木鉢です。 靴をモチーフにして制作してみました。 作家名 行雲(こううん) 制作工程はyoutube にて公開しています。 陶芸教室 陶八さんチャンネル https://m.youtube.com/channel/UC62ECLVxfkoq03yfWJqFlXA ぜひご覧ください。
-

陶芸・陶磁器 黒釉割型鉢003
¥12,000
黒釉で焼かれた陶芸・陶磁器の植木鉢です。 球体で作ってから割って表現しています。 作家名 行雲
-

陶芸・陶磁器 黒釉二段鉢
¥16,000
黒釉で焼かれた陶芸・陶磁器の植木鉢です。ロクロで土台をひいた後、さらに上にもう一段くっつけてます。 作家名 行雲
-

陶芸・陶磁器 黒釉小植木鉢
¥12,000
黒釉で焼かれた陶芸・陶磁器 小さめの植木鉢です。 足を付けて存在感を出してます。 作家名 行雲(こううん) 制作工程はyoutube にて公開しています。 陶芸教室 陶八さんチャンネル https://m.youtube.com/channel/UC62ECLVxfkoq03yfWJqFlXA ぜひご覧ください。
-

陶芸・陶磁器 白化粧長靴型鉢
¥18,000
白化粧で焼き上げた陶芸・陶磁器の長靴型の植木鉢です。 化粧の白さが目立ってますね。 作家名 行雲(こううん) 制作工程はyoutube にて公開しています。 ぜひご覧ください。