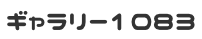2022/11/28 11:24
ここでは、陶芸の「やきもの」の伝統的に受け継がれてきた技法の一部を紹介します。
●糸切り高台
ロクロから陶器を切り離す際に、しっぴきと呼ばれる糸で
切り離すのですが、その時の切り離した跡をそのまま残す技法です。
通常、切り離した後に高台部を削って調節しますが、
手間を惜しんだかつての陶工たちが、
そのままの状態で作品として焼き上げたものが受け継がれています。
糸切りの跡はラセン状になっていたり、波目模様を描いていたり、
景色として鑑賞します。
●高台部に指跡を残す
ロクロから陶器を切り離して、器を移動する際に、
両手で「じゃんけん」の「ちょき」の形をして、作品を持ち上げます。
その時に高台周りにできた指跡をそのまま削らずに残す技法があります。
取り上げる時に指跡を残すのか考えて取り上げたり、
高台を削る際に指跡のきれいさに感嘆して、そのまま残したり、
各人によってさまざまです。
また、「やきもの」の高台まわりに釉掛けした際の
指跡を発見することがあると思います。
通常、釉掛けした後はその指跡を筆や指先に釉薬を付けて
消していくのですが、茶碗や徳利などで、わざと残したままにすることがあります。
また、高台の周辺の釉薬が掛かっていない所へ、
指に付いた釉薬をなびる事もあります。
知らない方が見ると、何ともいい加減な作り方だなと思うかも
知れませんが、この指跡を景色として鑑賞してほしいがために、
わざと残してあるのです。
手にした茶碗に指跡が残っていたら、
そこに自分の手の指をかざして、陶工の手クセを真似してみるのも
「やきもの」の楽しみ方です。
平凡な茶碗ではないよ、しっかりと手を掛けて作ってあるよと
作り手からの無言のメッセージなのです。
●高台部の目跡
釉薬を掛けた後に、窯入れして焼き上げますが、
陶器の底の部分に釉薬が付いていると、
焼成後に作品と棚板がくっついて取れなくなってしまいます。
それを防ぐために、作品を窯入れする時に釉薬の部分を丸く拭いて、
その部分に道具土と呼ばれる耐火度の高い土で、目を立てます。
陶器と棚板が離れて焼成できるので、くっつき防止になります。
企業などが作る量産陶器の場合はこんな面倒な事はしません。
最初から高台部に撥水剤を塗って、釉薬がのらないようにしたり、
スポンジでぬぐってそのまま窯入れをします。
つまり、目跡がある陶器は窯詰めに非常に手間をかけた、
大切にあつかわれた器であることの証明とも言えます。
●高台の見所
これは技法というより、鑑賞法なのですが、
「やきもの」に精通した人が陶器などを鑑賞する際に、
必ず裏返して高台の部分をじっくりと眺めます。
これは陶工のその作品に対する思いを感じ取っているのです。
高台の部分はロクロなどでの成型後に、カンナや木べらで削って調整するのですが、
その時に陶工の手クセや感性が非常にでやすい所なのです。
職人的に全てをきっちりと削る人もいれば、1点1点削り方を変える人もいます。
何がいいのかは一概に言えません。
量産品を作る時に一つずつ削り方を変えていたら、親方に怒られるでしょうし、
1点ものの作品を作る時には、変化に富んだ高台部にしたいでしょう。
すべては作った人の置かれた立場や、その時の状況にもよります。
陶工からすれば、その作品に対する思いを高台部から感じ取ってほしいのです。
そのため、鑑賞する時も裏をひっくり返して見てみると
何か新しい発見があると思います。
●貝やワラで緋色を付ける
やきもので緋色と呼ばれる色があります。
赤系だったり、オレンジ系だったり、土によっていろいろですが、
炎と土とが反応してできた非常にきれいな色です。
この緋色は信楽の黄瀬土などを薪を使って焼いた場合によく出てくる色です。
この色を意図した所に出したい場合に、貝やワラを置いて発色させます。
ワラを巻いたものでは、備前焼の緋だすきという技法があります。
備前の土でも緋だすきが出やすい土を使って、ワラをしっかりと巻きつけると、
その部分に見事な緋色が出てきます。
また、高台や器体の部分に貝を置いて緋色を出す技法もあります。
こちらはワラと違ってホンワカとしたやさしい感じの緋色に仕上がります。
●貝の跡を付ける
やきものの側面に貝殻の跡を見つける事があると思います。
釉薬が高温で溶けて流れた時に、貝に当たって貝紋様になる技法です。
陶器に灰釉などの流れやすい釉薬を掛けたり、
薪窯などでの自然釉が掛かった場合などは
器が窯壁や棚板にくっついてしまいます。
そこで、目土をかます方法もありますが、
目土だと目土本体に釉薬がくっついてしまう場合があります。
そこで、貝の登場です。
貝に釉薬が流れ込んでも、貝跡として景色になるし、
焼成後に水に漬けておくときれいに貝が溶けてしまいます。
多分、昔の陶工は色々な材料を試したのだと思います。
その結果一番良かったのが、この貝殻だったのではないでしょうか。
流れやすい釉薬を使う場合には必需品の技法なのです。